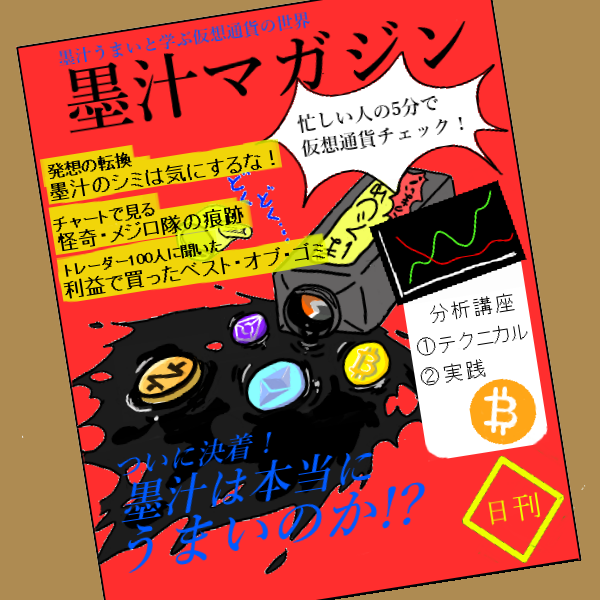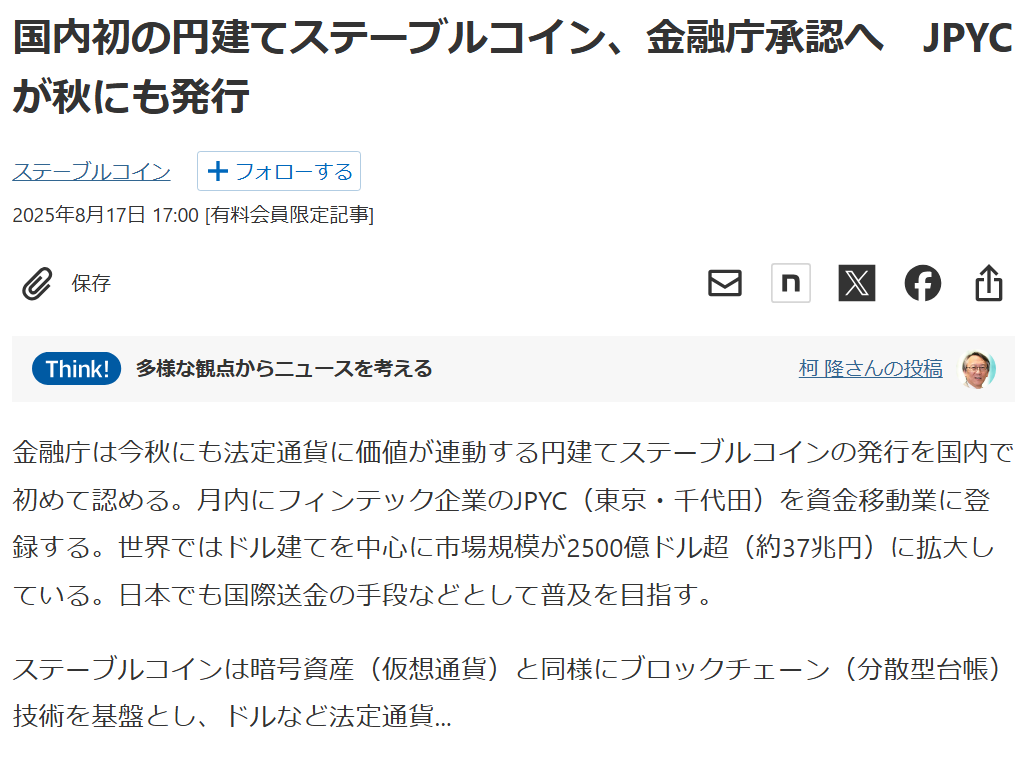イーサリアムエコシステムのDeFiのコアプロダクトとなるサークル社のUSDCやテザー社のUSDTに代表されるステーブルコインは、金融庁の承認によりイーサリアム上で発行される「JPYC」がはじめて承認されました。
これによりステーブルコインが日本の仮想通貨(暗号資産)界隈で話題となっており、需要の増加が見込まれます。本稿ではJPYCの利点とリスク、DeFiへの影響について仮想通貨(暗号資産)投資家向けにわかりやすく解説を行います。
ステーブルコインビジネスについては墨汁マガジンVol.1106「USDCのCircleはなぜIPOをどうしても行いたかったのか?ステーブルコインビジネスを理解する」を参照してください。
円ステーブルコインの「JPYC」が金融庁承認
日経の報道によると金融庁はイーサリアム上で発行されるERC20トークンで、円の裏付けを持つステーブルコイン「JPYC」の発行を承認したと報道しました。
これにより日本で初めての金融庁承認のステーブルコインが誕生し、この背景には米国でのUSDC発行を行うサークル社の上場や各種ステーブルコインビジネスの加速が仮想通貨推進派のドナルド・トランプ大統領により実現したことが大きな理由と言えるでしょう。
この承認によりステーブルコイン対応が国内でも急加速しており、クレジットカードなどでのJPYC利用ができるようになるとされています。
ステーブルコインのETH影響については墨汁マガジンVol.1167「ステーブルコイン導入ムーブがイーサリアム(ETH)を1万ドル以上を押し上げる理由」を参照してください。
JPYCは新規プロジェクトではない
$JPYCはJPYC株式会社が発行する円ステーブルコインですが、新規プロジェクトではなくその歴史は古いのです。実はJPYCは2019年11月に法人を設立しており、代表の岡部氏は自分の記憶では2018年前後から日本でのステーブルコイン発行で動いており、
「資金決済