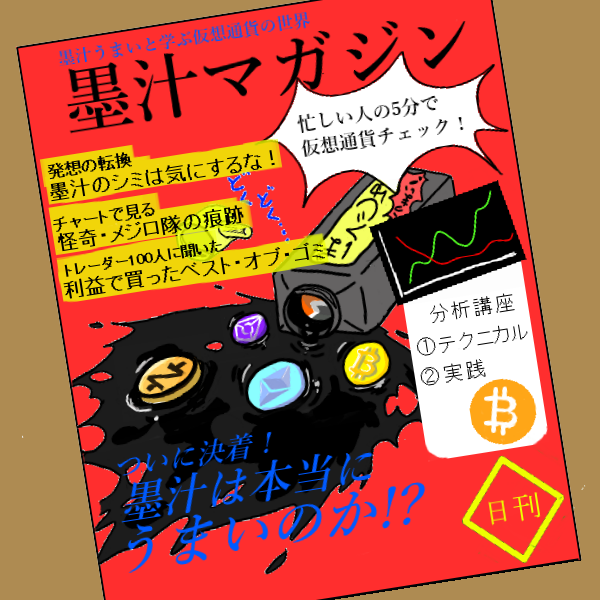- 1 金融庁仮想通貨の取扱いを有価証券並みへ
- 2 日本におけるこれまでの仮想通貨の取扱いと規制
- 3 日本における仮想通貨規制の間違い
- 4 総合課税で55%の最大税率が妥当である理由
- 5 国民の理解が得られないといわれた理由
- 6 仮想通貨を有価証券並みの取扱いにする利点
- 7 仮想通貨分離課税実現への影響は?
- 8 まとめ
金融庁は仮想通貨(暗号資産)の取扱いを有価証券と同等まで引き上げる検討に入っていることが日経のリーク報道で判明しました。本稿ではこの日本での仮想通貨の取扱いが変更することにより現状の最大55%の税制から分離課税となる20.315%の実現への影響、個人の仮想通貨投資家における今後の影響について仮想通貨(暗号資産)投資家向けにわかりやすく解説を行います。
現状の仮想通貨税制変更の課題については墨汁マガジンVol.1058「仮想通貨(暗号資産)の分離課税はいつになる?税制改正に必要なことと問題点」を参照してください。
金融庁仮想通貨の取扱いを有価証券並みへ
日経のリーク報道によると、日本の金融庁は仮想通貨(暗号資産)の取扱をこれまでの決済手段から有価証券並みに引き上げることを検討する意向であることが判明しました。
その理由としては
「事業者により詳しい情報開示を求めて投資家保護を図る目的。仮想通貨で運用する上場投資信託(ETF)の解禁を視野に活用の促進にもつなげる」
としており、国内での仮想通貨ETFの承認を視野に入れた動きであるとされています。
この動きの背景には米国における仮想通貨推進派のドナルド・トランプ大統領の就任や米国証券取引委員会(SEC)による仮想通貨現物を運用するビットコインETFとイーサリアムETFの承認、ブラックロックやフィデリティを中心に既にゴールドETF並みのAUMで需要が明確であることなどが理由と言えるでしょう。
日本におけるこれまでの仮想通貨の取扱いと規制
これまでの日本における仮想通貨の取扱いは問題があり、2016年に可決し2017年4月施行された資金決済法での規制により「決済手段または前払い手段」として取扱いが位置づけられました。
また2016年次点では世界各国における仮想通貨規制は明確ではなく、米国が2025年現在も明確な規制を持たず、トランプ政権発足から急ピッチで米国証券取引委員会(SEC)や米商品先物取引委員会(CFTC)などの規制当局の人事、ワーキンググループなどで整備しているように、日本の法整備は世界各国の動向を元に決めたことが現在の仮想通貨後進国へ衰退した理由となっています。
仮想通貨規制はFATFの2019年のKYC強化までは仮想通貨取引所の登録制の必要性を訴えていたものであり、それらとヨーロッパ諸国の対応を加味していち早く「暗号資産交換業者(仮想通貨交換業者)」を導入したわけですが、これらに伴い上場のグリーンリストの導入から日本は2017年時点で世界に取り残されることになるのです。
日本における仮想通貨規制の間違い
日本における仮想通貨規制の間違いは、
「仮想通貨